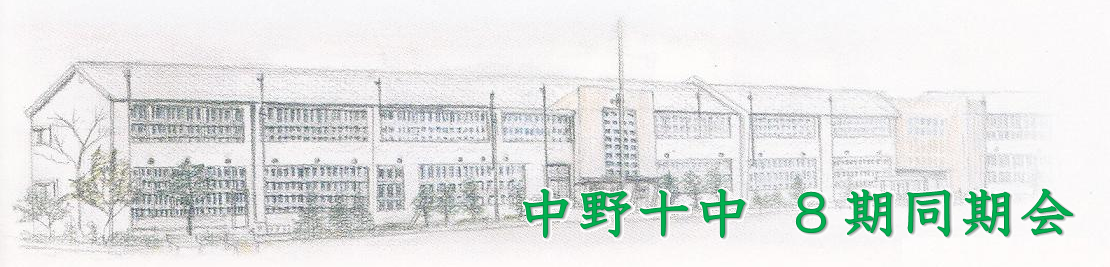昭和三十一年の春、東京芸術大学の四年生だった私に、大学の学生課から呼び出しがかかった。中野区立のJ中学校が音楽の先生を求めており、男で作曲科の卒業生を探しているが、行く気はないかとのこと。
卒業作品の完成しか念頭になかった私は、「卒業したら働かんならんのや」ということに、この時初めて気がついた。「しかし、作曲では食うてゆけそうもないし、やっぱし学校の先生シカあかんやろうな。よっしゃ、先生にデモなるかー」
後に「デモシカ先生」という言葉が流行した時、私はまるで自分のことをいわれているような気がした。
国鉄中央線の東中野駅を降りると、J中学はすぐに見つかった。
大学での一年先輩に当たるN先生に会い、彼女の仲介で校長先生の面接を受け、東京都の教員試験に合格したらきてもらいましょうーということになった。
その試験に無事合格し、昭和三十一年四月、私はJ中の音楽教諭になったのである。
この学校は、私が赴任した四月に創立三年目を迎え、全学年が揃ったところだった。
現在では信じられないことだが、校長四十一歳、教頭三十八歳、教員の最高年令は家庭科のE先生四十八歳、学年主任が揃って二十九歳、その他は新卒ホヤホヤが大半を占め、平均年令二十六・五歳、自分達の手で学校を作るんだという熱気が学校全体に溢れていた。私は三年生の副担任に配属され、さしたる気負いもなく教員生活を始めた。

さて、私が受け持つことになった三年D組に、キンちゃんという生徒がいた。彼は早くに両親を亡くし、ペンキ屋のおじさんの元で育てられているのだった。勉強が嫌いなのか、或いは解らないまま中学三年生まで来てしまったのか、キンちゃんはいわゆる「クラスのお客様」的存在だったが、憎めない性格のゆえに皆に愛されていた。
音楽の時間は生徒達にとって息抜きの時間である。いわゆる主要五教科から解放された生徒達は音楽室の扉をガラガラッと開け、机と椅子をとびこえて教室になだれこんでくる。私は理屈抜きの楽しい授業にしたいと工夫し努力したが、生徒にとってはまず何よりも、新米でドジばかりふんでいる私の存在そのものが「楽しみの対象」なのだった。
解放された気分も手伝って、彼らは少しもじっとしていないし、静かにしてもくれない。私はつい騒々しい生徒を廊下に立たせることにした。しばらくして教室にいれてやるつもりで廊下に出ると、彼がいない。あわてて探しにゆくと、向こうからゆっくりと歩いてくる。
「どこへ行っていた!」
「便所に行ってました」
新米の私はそこでブッと噴きだしてしまい、教室はドッとわきかえる。これにこりて、次からは教室の後ろに立たせることにした。
或る時、女子生徒年でヒソヒソ話し合っているので注意すると、男の子達が「先生は男ばかりを立たせて、女に甘い」と、この時ばかりはクラスの優等生も一緒になって抗議し、私がどうするか一斉に息を殺して見守っている。私は仕方なく彼女達を教室の後ろ立たせた。授業が終わると二人はワッと泣き出しながら教室をとびだして行き、翌日は揃って欠席した。
担任のS先生が家庭訪問すると、朝はいつも通りに家を出たとのことで大騒ぎになったが、夕方二人はケロッとして家に戻り、上野の動物園で象を見てきたと言った。
「すみません、御迷惑かけてしまって」と私。
「いえ、いいんですよ」。S先生は笑って慰めて下さった。
それでも生徒達は、上手に持っていけば、よく歌い、静かにレコードも聞いてくれた。
ところで、その頃の高校入試はアチーヴメントテスト方式だったから、筆記試験に備えて音楽理論もみっちりやっておかなければならなかった。生徒達も進学につながるので、結構集中して授業を受けていた。
さて、キンちゃんである。
歌の時にほ皆と一緒に生き生きと歌っているが、理論の時間には取り残されてしまう。全く解らないし、面白くもないし、退屈だから一番後ろの隅の席で、机と椅子をギッコンバッタンゆすりはじめる。ゆすりながらひそかに私の顔色を伺っている。
だから私はキンちゃんの期待に応えてやらなければならない。頃合いを見計らって私は恐い顔になり「コラ!キンちゃん!」とにらみつけてやる。
彼はギッタンバッタンをゆっくりとやめて、至極満足そうに私を見つめ、ニーッと笑う。その笑顔があまりにも可愛く、あまりにもおかしいので、私はこらえ切れずに、またまたブッと噴き出してしまう。
その瞬間に音楽理論の時間の固い雰囲気が消え、クラスの隅々まで緊張がほぐれてゆくのが、肌で感じられるのだった。
学期末になるとこんなキンちゃんの元へ落ち葉が吹き寄せられるように、五段階評価の「1」が集まってくる。
「可哀そうだなあ」「でも、どうしようもないわね」と先生達は話し合う。ほんとうに、これだけはどうしようもないのだ。
せめて音楽だけでもキンちゃんを救ってやりたいが、その為には誰かが「1」を引き受けなくてはならない。どの子も高校受験に向かって精一杯やっている。「2」の女の子は「3」になって、私に認めて貰いたい一心で、これも頑張っている。困ったな。そんな時、机と椅子をのんびりゆすっているキンちゃんの屈託のない顔が浮かぶ。
「ゆるせよ、キンちゃん」

私は私は彼の名前の欄に重たく「1」とかきこむ。
「いいよ、しかたがないよ」朴訥な担任のMさんが私達同僚を慰めてくれる。
でも、先生達は皆キンちゃんを可愛がっていた。二年生だった時、担任だったTさんの沼袋の家をキンちゃんは休みの日に、探し探し訪ねていった。Tさんは喜んで彼を迎え、彼女のご主人も一緒になって彼と遊び、子供のいないTさん夫婦は、とうとう彼を一晩泊めてやったという。
夕方、勤めを終えた私達が校門を出て都電通りの方へ歩いてゆくと、キーンとはりつめた声が道路の向こう側から聞こえてくる。
「センセーイ!」
見るとサッソウと自転車に乗ったキンちゃんが、こちらを向いて手を振りながら走ってゆく。車の後ろにはペンキの缶と刷毛をくくりつけている。学校から帰ると早速に、おじさんの家業を手伝っているのだ。
ああ、この子はもう早や手応えも確かに自分の生きていく道をつかんでいる。学校の成績なんか、この子には関係ないんだなーと、いささか自己欺瞞の後ろめてさを意識しながらも、私はホッとするのだった。
修学旅行は奈良・京都へ。
新幹線のまだない時代、在来の東海道線を往復車中泊の旅だった。副担任の私は生徒達に溶け込んでワイワイガヤガヤやっていたが、ふと独りになりたくて、空いている隅の席に移り、ぼんやりと車窓の景色を眺めていた。
そこヘキンちゃんがフラリとやって来た。
「先生、こんな歌知ってる?」と小ブシを利かせて歌い始めたのは、三橋美哲也の「新撰組の歌」である。
「キンちゃん、うまいな!」。
お世辞でなく私か褒めると、彼は満足そうにニーツと笑い、「いい歌だろう?俺教えてやっから、先生も覚えなよ」
キンちゃんは真面目な顔で一節づつ歌い、私にあとをつけさせる。いつの間にかクラスメイトも集まってきて合唱になる。
得意になって歌いつづけるキンちゃんを眺めながら私は考える「1」を一手に引き受け、理論も解らず楽譜も読めないキンちゃんが、音程もリズムもはずさずに、何よりも歌の心をしっかりつかんで歌っている。
音楽教育っていったい何だろう?
フツウの町並みの中のフツウの学校、そしてフツウの生徒達-このフツウずくめが私にはとても新鮮であり、私の卒業した大学がフツウでなかったことを改めて認識した。
大学で習ったことが、そのままではほとんど通用せず、しっぺ返しの連続であった。
音楽を専門に勉強してきた者と世同一一般との落差の大きさを思い知らされ、フッウの人々にとって音楽とは何なのかを、根源にさかのぼってつくづくと考えさせられた。
しかし、あれだけ密度濃く勉強してきたことと毎日の生活との落差もまた、折に触れて私を悩ませた。このままでいいのだろうか。
大学の四年間はいったい何だったのか?
一年間があっという問に過ぎた。
第一回の卒業生を送り出した後、校長先生から「来年度はクラスを担任してもらうよ」と言われた矢先、親元から電報が来た。
神戸大学教育学部の音楽科に空席ができ、作曲・理論の担当者を求めていると、恩師のO先生から知らせいただいたが、帰って来ないかとのこと。
当時の私はまだ、東京にいること白体が魅力であり、恩師の配慮には感謝しながらも、迷いに迷った。
ちょうど、弟が大学を卒業し就職の為家を離れたばかりのところで、長男の私に戻って来て欲しがっている父の気持が、私には切なく伝わってきた。私は決断した。
大学では、中学に比べて、教えることも、今まで勉強してきたことのつながりが密接にあるし、作曲する為の時間と気持のゆとりもできた。

やがてJ中で同僚だったTさんの詩を合唱曲にしたものが、文部省主催の芸術祭・作曲募巣に入選し、その初演に立ち会うため、私は上京した。J中の同僚達が、お祝いをかねて集まってくれることになり、Tさんが会場への案内かたがた迎えに来てくれた。
「ちょっと、前以て言っとくけれど、今J中では勤務評定の賛否を巡って、職場の意見が二つに割れているの。人問って分からな
いものね。あんなに仲のよかった先生達が、意見の違う相手とは口も利かなくなってしまったの。泣きたくなるわ。今日はE先生
とY先生もいらっしゃるけれど、それはあなたのお祝いの為だからで、私達普段はお話もまともにできない間柄なのよ。ようくお願い
しとくけど、今日は勤評闘争のこと、絶対話題にしちやダメよ。せっかくの会がメチャクチヤになっちゃうから。いいわね?」
勤評闘争のことは、教育学部にいる以上知ってはいたが、義務教育の現場がそれほどまでに生臭い状態になっているとは知らず、私は身の引き締まる思いで会場へ向かった。
しかし案ずるほどのことはなく、かつての同僚達は、お互いになごやかに、昔の思い出話に打ち興じて時を過した。
その後も私は上京のたびに同僚達に会い、かつての生徒達の消息も話題になったが、いつも時間に追われて神戸一東京間を往復
し生徒達に会う機会はなかった。
それから:二十年近く経った或る日、J中での教え子だったEさんが、ひょっこりと神戸の私を訪ねてくれた。彼女は、甲子園で高校野球をみたいという息子を連れて、大阪の親戚へやって来たのである。
一児の母なのに、私の前に現れた彼女は、中学三年生のままの「旧姓Hさん」だった。
実は第一回卒業生の同窓会を計画しているので、私にも来て欲しいという。是非出席する、と私は答えた。
「先生、誰にいちばん会いたい?」
こういう女のコ的質問には、教師をハッと身構えさせるものがある。しかし私は、ためらうことなく、キンちゃんの名を挙げた。
「じゃあ、彼にそう伝えとく」
Eさんは約束して帰っていった。
二十年ぶりの同窓会には、新幹線による日帰りながら、やっと都合をつけて参加した。
かつての生徒達は三十歳台の後半にさしかかり、早く結婚した女性の場合、子供は中学生になっているという。
いたずらで私を困らせた悪ガキたちが、いいオッサンになり、元校長先生の挨拶を一列に並び、直立不動の姿勢で聴いているのも微笑ましかった。
学校を休んで、上野の動物園へ象を見に行ったKさんも、落ちついた主婦になっていた。
「憶えてる?」「憶えてます」
私達の会話はそれだけで十分だった。
「どうしたの?」「何かあったの?」
友人達が不思議かって尋ねたが、Kさんは黙ってニンマリと笑っていた。
「先生、連れて来たわよ」
Eさんの声にふりむくと、そこにキンちゃんが立っていた。彼は体に合わない背広を着て、こころもち緊張しており、私は何を話してよいのか判らなかった。
「元気?」「うん」「Eさんから聞いてくれた?」「うん。だから僕、来たよ」
今はペンキ屋の親方であるキンちゃんが、中学三年生のままで、私の前に立っていた。
さらに数年経ちJ中は創立三十周年を迎えた。
敷地は昔のままながら、高層ビルに取り囲まれて、かつてのような見渡す限りの空はなく、私達の時代の木造校舎は、白い鉄筋の三階建にとって替られていた。
その体育館で行われた記念式典で、私はTさんの詩に作曲したJ中の校歌を久方ぶりにピアノで伴奏し、皆で斉唱した。
式典のあと私はかつての同僚達や第一回の卒業生達と再会し、会食した。
私達が新宿西口の雑踏を歩いている時、Eさんが寄ってきて、ポツリと言った。
「先生、キンちゃん死んだのよ」
「えっ?」。
私は思わず問い返した。
「…建築現場で足場を踏みはずして…。人も使って、仕事もうまくいっていたのにねえ…。
少し過労気味で、眼が見えにくくなってたんだって。そんなに働かなくっていいから、人に任せて休め休めって、まわりの人は言って
たらしいのよね。お葬式に行ってきたけど、ほんと、可哀いそうだったわ…」
了
神戸新聞 昭和63年7月22日 掲載 [エッセー部門入選作]
昭和31年~32年 中野十中に音楽担当教諭として在任された中村茂隆先生の生徒との交流を綴られた心温まるエッセーです。
中村先生は在任中に当校の校歌も作曲されました。