外国。ガイコク。
何と魅惑的な響きだったろう。ガイコクの地を踏んだら、感激のあまり卒倒するであろう、と僕は確信していた。
一九七三年の初夏、生まれて初めての外国、旧ソ連のナホトカの波止揚のコンクリートを踏んだとき、関税を通過する緊張感で、卒倒するのも忘れていた。二十三歳だった。
横浜を、ジェルジンスキー号というソ運船で出港した。友人数人と両親が見送りに来た。
紙テープを役げて彼我でそれを握り合っていたのは、他の客達も同じだった。当時、飛行機よりもこのシベリア経由のほうがいくらか安かったのである。
ふと隣を見ると、ジャンパー姿の二十五、六の男がテープも持たずに立っている。テープを持って手など振り合っている人々を、どこか冷笑的に見下している様子に感じられた。旅慣れているんだなァ、と思っだのだが、それよりも、旅慣れたように見られたいのだな、ということが段々わかってきた。あとで少ししゃべったら、実は彼はただの旅でない、ヨーロッパヘは以前も行っていて、今回は、そこで行方不明になった友人を探しにいく旅だという。
ふーん。僕は感心したが、その大義名分にへきえきしてしまって、それきり彼とはしゃべらなかった。
船で同室だったのは、宮崎君という同年齢の男で、やはりジャンパー姿に、つっかけをはいていた。つっかけ以外のはきものは持っていなかった。面白い男で、いろいろ世間的なことをよく知っていた。知っている、ということが面白くてたまらないらしく、それを僕のような未熟な者に教えるのも好きらしかった。
「五木寛之を読まなくちゃダメだ」
とよく言った。僕はそれを読んでいなかった。思い出すと、僕はその頃、キルケゴールの『死に至る病』とか、ニーチェの『ツァラトストラかく語りき』とか、カミュの『異邦人』とか、サン=テグジュペリの『夜間飛行』とか、稲川足穂の『弥勒』とか、を読んでいた。
横浜港でテープを握っている問に、気づいたのは、陰気な例の友人探しの男のむこう側で、陽気にさわいでいる三人の若い白人達だった。眉を剃ってしまったような風体の変な一行だった。
夕食のあと、サロンでボーイが歌うというので行ってみた。船上にでは酒類は無税で安かったので、ブランデーの杯なんぞを片手に、サロンに座った。西洋人が二十人ほど、日本人が十人ほどいた。ギターを持って出てきたのは、さっきの眉のない白人の一人であった。弾き語りでたくさん歌ってくれた。歌は上手いのに、風体が妙なので今ひとつ中に入り込めずに、眺めていた。近くの人に歌い手の名をきくと、
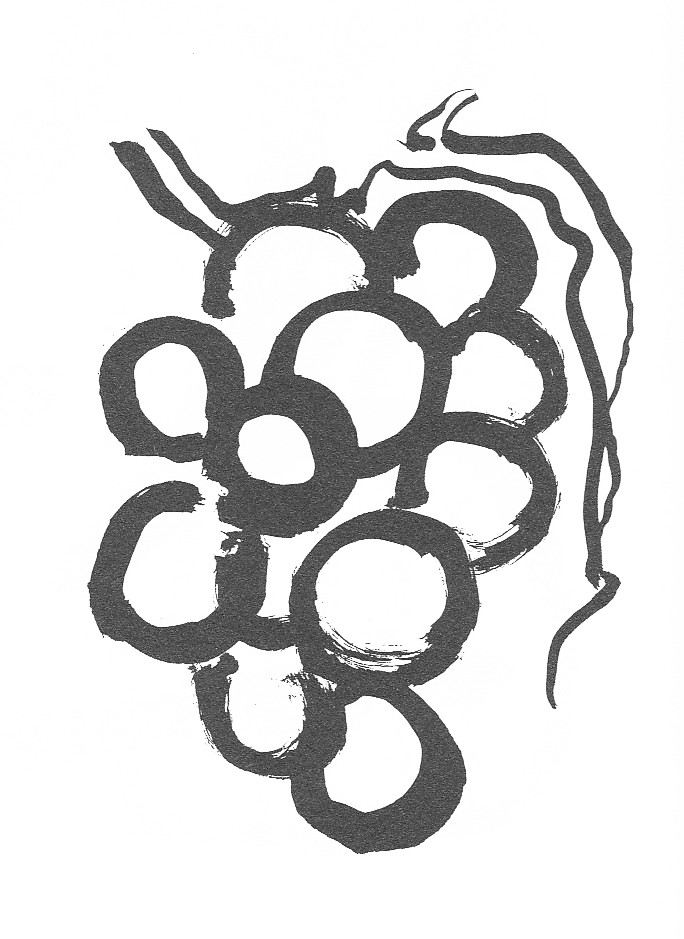
「デビッドーボウイ」
と教えてくれた。僕は、それが何かのボーイだと、まだ思っていて、
「ふーん」
と言った。歌が終わると、そのボーイは西洋入のおばさん達に囲まれてソファに座っておしゃべりしていた。その仲問の一人と、僕はバーのカウンターでブランデーを飲みながら、片言の英語で何やらを語り合った。彼はさっきのボーイの楽団でドラムスをたたいているのだと言った。
「じゃ、このジャ八二ーズー・リズムは知ってるかい?」
と言って、僕は八丈太鼓のリズムを箸でたたいてみた。八丈島へ遊びに行って、僕はそれを一晩で覚えたのが自慢だったのだ。下拍子が単調なリズムをたたくと、上拍子が大太鼓の反対側をアドリブでいろいろ面白くたたいてゆく。上と下の拍子がひとつの太鼓の中で複雑にからみ合う、勇壮な鳴り物である。そのドラマーは、打ち方は違うけれども、一種類のほうは同様に聞こえるように打てた。が、もうひとつのリズムのほうはついに出来ずに、口惜しそうな顔をした。
ドラマーのくせに何故こんな簡単な打ち方が出来ないのだろう、と僕は不思議だった。簡単なことであるほどに日本と西洋では違うことがあるものだと、その時は思わなかった。






